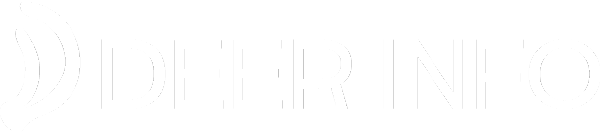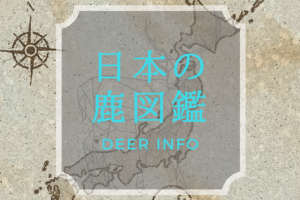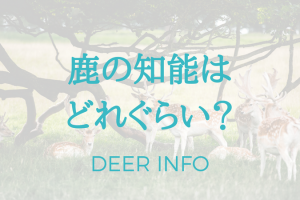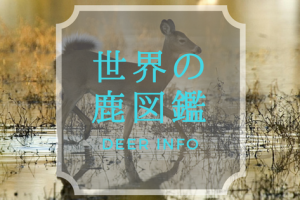ししおどしとは
ししおどしは漢字で「鹿威し」と書きます。
音で鹿などの野生動物を驚かせて、人間の住んでいる場所の近くから追い払うために考案された装置です。
ししおどしは一般的には、
- 竹の筒に細く水を流す
- 筒に水が溜まると竹が傾く
- 空になった竹がもとの位置に戻る時にカポーンと大きな音が鳴る
- 鹿などが驚いて逃げていく
という仕組みになっています。
別名「添水(そうず)」とも呼ばれます。
ししおどしの歴史
ししおどしは、京都にある詩仙堂という寺院が発祥の地とされています。
詩仙堂は1941年に徳川家の家臣だった石川丈山が隠居のために作った建物です。
ししおどしを考案したのは石川丈山だと言われているため、ししおどしが誕生したのも1941年(昭和16年)前後のことでしょう。
意外と新しいですね。
夜間頻繁に出没して詩仙堂の周りの畑を荒らしていた鹿やイノシシはこのししおどしの登場によって詩仙堂に近づかなくなったそうです。
ししおどしの効果
詩仙堂に設置されたししおどしに鹿やイノシシを追い払う効果があったことからもわかるように、初めてししおどしの音を聞いた野生動物は驚いて逃げ出します。
ただ、動物には学習能力があります。
同じ音を何度も聞けば、「この音が鳴っても特に危険はないぞ」ということを学習してしまいます。
そのため、長期的な鳥獣除けの効果は薄いです。
現代においては鳥獣除けというよりは人間が癒し効果を得るためにししおどしを置いているパターンのほうが圧倒的に多いです。
水の流れる音とたまに響く竹の「カーン」という音に日本ならではの風流を感じますね。